高級嗜好品として珍重され、酒肴として賞味されることが多いからすみ。主にボラなどの卵巣に塩をまぶしてつくる塩乾品である。古来よりギリシャやエジプトで食され、日本には中国から16~17世紀に伝わり、江戸時代、ウニやこのわた(ナマコの腸の塩辛)と並び「天下三珍」と讃えられた(『長崎県文化百選 事始め編』長崎新聞社発行)。当時から肥前国(現在の長崎県および佐賀県)、特に野母(現在の長崎市野母町)産のものが有名である。茶道では新年の茶会で懐石の肴に用いられ、江戸期の狂歌師・大田南畝(おおたなんぽ・1749~1823)がその味を絶賛した歌が今に残る。
さて、「からすみ」という呼び名は、その形が唐(中国)の墨に似ていることから付けられたとされている。それを名付けたのは、戦国時代の名将で、のちに佐賀藩の礎を築いた鍋島直茂(1538~1618)であるといわれている。では、この鍋島直茂とは、いかなる人物であったのであろうか。今なお多くの人々を魅了する珍味・からすみをめぐる歴史とともに紐解いていきたい。

鍋島直茂肖像(財団法人鍋島報效会 提供)
戦国時代、肥前国を根拠地として九州に割拠し、「肥前の熊」と呼ばれた竜造寺隆信(1529~1584)。その片腕として仕え、類い希なる知略と統率力で、強大な豊後国(現在の大分県)の大友氏、薩摩国(現在の鹿児島県)の島津氏らと並ぶ勢力までに主家を導いたのが鍋島直茂である。1570(元亀元)年、大友氏は竜造寺氏討伐の兵を挙げ、大軍をもって領内に攻め込んだ。6万ともいわれる大友軍に対し、竜造寺軍は5千あまり。この時、直茂は寡勢をもって敵本陣に夜襲をかけ大勝、主家の危機を救った(今山合戦)。優れた軍略と政治力を発揮し、家中における地位を確立した直茂は、以降、家臣団の上層に位置し続けていたことが、竜造寺氏の侍帳(大名家の家臣や役職を記した公的な帳面)『隆信公幕下着到』からうかがえる。
1584(天正12)年、竜造寺隆信は沖田畷(おきたなわて)で行われた島津氏との合戦で敵の計略にかかり戦死してしまう。隆信の本体側面で戦っていた直茂は優勢に戦を進めていたが、総大将の戦死で混乱した味方の退却に巻き込まれ、撤退を余儀なくされる。帰国後、隆信の子である政家が跡を継ぐと、直茂は優秀な指導者を望む家臣団に支持されて、若い主君を補佐しつつ実権を掌握する。その後、天下統一に邁進する豊臣秀吉(1537~1598)の九州征伐にいち早く随行。誼を通じ、1588(天正16)年には、竜造寺家とは別に、長崎周辺を管轄する地方代官に任命されている。直茂が「からすみ」と名付けたエピソードはこの頃のもので、以下のように伝えられている。
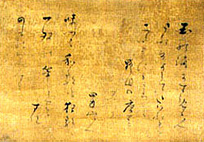
大田南畝が勘定方として長崎奉行所へ赴任した際、好物のからすみについて歌った歌が、今も掛け軸として残っている。
『玉の浦に住める人ざれ歌よみてたまれと 名を乞ふままに、所から野母のからすみと名づくとて、味わいは和歌も狂歌も一双の 筆とりてすれ野母のからすみ』(高野屋 提供)
天下人・秀吉が朝鮮出兵の準備で名護屋(現在の佐賀県唐津市鎮西町名護屋)を訪れた際に、長崎代官であった直茂がからすみを献上。その味に感嘆した秀吉が「これは何という食べ物か」と尋ねた。すると、直茂は機転をきかせ、「ボラの卵」とは言わず、「唐墨(からすみ)でございます」と答えた。唐(中国)の墨の形に似ていたので、その形を例えたのだ。頓知が大好きな秀吉はこれを喜び、以降、からすみはその名で呼ばれるようになったという―。
しかし、1928(昭和3)年創刊の史的研究誌『長崎談叢(ながさきだんそう)』によると、このエピソードの真偽は確かではないようだ。その少し前の1585(天正13)年、秀吉が関白となって参内した折の食膳献立記録のなかに「カラスミ」の名が記されている。そのため、この時代、宮中にあっては既にからすみの御用があったと推測されるのである。
また、からすみの「直茂起源説」は伝承のみで、それを裏付ける明確な史料は見つかっていない。恐らく、切れ者であった直茂らしい逸話として、彼を愛する地元の人々により、地場の特産と結び付けて語り継がれてきたのであろう。
ちなみにその後の直茂は、秀吉や家康といった天下人に認められ、竜造寺氏の家督を相続。やがて国政委譲により、明治まで続く佐賀藩が成立することになる。
ところで、直茂の活躍していた時代、特に1600年以降には、日本と中国との交流は活発に行われており、食をはじめ多くの大陸文化が窓口である長崎に流入した。そして、主客ともども円卓を囲み大皿に盛られた料理を食する唐風の卓袱(しっぽく)料理をはじめ、異国の食に触れる機会も自然と増えていった。その頃のからすみは、当初、ボラではなく鰆(さわら)の卵巣を使っていた(『長崎県文化百選 事始め編』長崎新聞社発行)。色合いも、現在の物よりやや黒ずんでいたという。それでも美味だったようで、秀吉の後に天下人となった家康により、朝鮮通信使が再び招かれたが、その饗応の献立にからすみが含まれていたことも分かっている。
やがて17世紀後半になると、長崎万屋町の魚屋・高野勇助が、ボラの卵巣を塩漬けにしたからすみをつくるようになり、その味が評判となった。彼の店でつくられるからすみは長崎奉行から宮中や幕府に献上されるようになり、その慣習は明治維新まで続いた。

高級嗜好品として日本で賞味されているからすみだが、国内産の原料は限られていることもあり、現在はブラジルや台湾、オーストラリア産のものも多い。
とはいえ、からすみ自体は高価で、庶民の口にはなかなか入らなかった。というのも、その生産には、非常に手間がかかったからだ。からすみをつくるにはまず、ボラの卵巣を皮膜を破らぬよう気をつけよく洗い、3~6日間樽に塩で漬ける。数日後、取り出した際に丁寧に付着物を除く。そこから一昼夜おいた後に水で洗い、塩抜きをしなければならない。数ある作業のなかで、この塩抜きの調節が困難を極め、この作業で味が決まってしまう。そしてやっと卵巣を厚板に挟み込み、数日ほど寒風に吹きさらして乾燥させ、ようやく完成するのだ。
他にはない独特の風味と濃厚な味わいは、こうして多数の工程を経てつくり出される。今も昔も変わらずからすみが高級品であり、大量生産できない背景には、こうした手間暇と、熟練の技術が必要とされる部分が大きい。
異国に開かれた町・長崎だからこそ伝えられ、根付いたともいえるからすみ。以前は主に正月用の食として用いられていたが、現在は冷凍技術の発達により、1年中食することが可能になった。それでも手軽に食べられる珍味、というわけにはいかないが、食する際には、からすみにまつわる偉人たちに思いを馳せてみてはいかがであろうか。