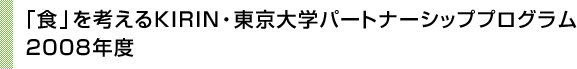2008年度は、第一歩として「食への関心」を取り上げました。食べ比べなどの食体験も交えながら、一番身近な食卓から発想し、「食の未来」のために私たちにできることはないか、様々な角度から考えました。
キリン食生活文化研究所は、
1月15日「米櫃が底をついた日のこと~江戸における飢饉と『食』の知恵」と題して
第3回ワークショップを開催しました。
| 日時: | 2009年1月15日(木)16:20-17:50 |
|---|---|
| 場所: | 東京大学駒場キャンパス 101号館 |
| 講師: | ロバート・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科教授 |

- ■江戸期の医者で文人の畑銀雞(はたぎんけい)の「御代乃寶(みよのたから)」(1833年刊)に記された、米を蕪と豆で増量したレシピの蕪飯を試作・試食した。食は滋養のためという考え方や飢饉の備えを庶民に紹介した「救荒本」を実際に紐解きながら、当時の生活を垣間見、鎖国当時の日本人が日本の風土や米に自信を持っていたことを知った。
- ■歴史から食を学ぶ視点や寺・神社でのフィールドワークの方法などを、アメリカ生まれで日本在住20年余のキャンベル先生が惚れ込んだ銀雞の人柄も交えて、興味深いお話をうかがった。
- ■江戸期は生活の知恵などを記した冊子が、「施本」と呼ばれ、個人や藩から無料で配られたが、明治以降に活字化された資料が少なく江戸期の「食」に関する研究はほとんどされていないという。
* 天保の大飢饉(てんぽうのだいききん)は、江戸時代後期の1833(天保4)年に始まり、1835(天保6)年から1837(天保8)年にかけて全国に広まった飢饉である。

- ・銀雞のふざけながらも人々のためを思い試行錯誤する人柄に興味を持った。
古書を手に取ってみて、先人の世界に触れてみるのはおもしろいと思うようになった。 - ・少ない食料を有効利用する知恵を多くの人と共有することに感心した。
日本人を誇りに思った。贅沢すぎると自覚した。 - ・米が日本人としての意識をつなぐものだったかもという話に驚いた。

「蕪飯の炊き方」※現代語に意訳
蕪を細く刻んで塩水で洗い、米一升に蕪五合と味噌豆二合を入れ、
米と混ぜて炊く。
水加減は通常通りでよい。
なぜなら、蕪から水が出るので、ほどよく豆も煮えるからだ。
この調理法は上州伊香保の人に伝わるもので、非常に風味もよい。
なお、豆は宵のうちに水に浸しておく方がよい。