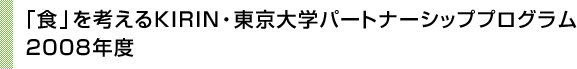2008年度は、第一歩として「食への関心」を取り上げました。食べ比べなどの食体験も交えながら、一番身近な食卓から発想し、「食の未来」のために私たちにできることはないか、様々な角度から考えました。
キリン食生活文化研究所は、
3月9日茨城県水戸市にある「鯉淵学園農業栄養専門学校」で農業体験による
第5回ワークショップを開催しました。
| 日時: | 2009年3月9日(月)11:00-16:00 |
|---|---|
| 場所: | 鯉淵学園農業栄養専門学校 |
| 講師: | ボカシづくり:涌井先生、ジャガイモ作付け:丸石先生、きゅうり整枝:及川農場長 |


- ■ボカシ(有機肥料)づくりは落ち葉や鶏糞、米ぬか、処理した生ゴミなどを混ぜ合わせるもので、触ってにおいを嗅いでも臭くなく、細かく砕いてから丁寧に混ぜ合わせました。握って形が残る程度の水を含ませ筵(ムシロ)の下に保管。発酵で熱が発生していました。天候や気温も影響するので、「マニュアルは通用しない」という講師の言葉に農業の厳しさも実感しました。
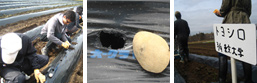
- ■ジャガイモは「北海道産トヨシロ」の半分の切り口に灰をまぶしたものを黒のポリエチレンフィルムの穴に、5センチの深さになるように切り口を下にし、隙間無く土をかぶせました。浅すぎても深すぎてもうまく芽がでないという説明に気を配って作付けしました。

- ■きゅうりの整枝作業はハウスの中で行いました。整枝は病気を予防し、まっすぐにきゅうりが形良くのびるために、無駄な葉や蔓を摘み採りました。葉を取ることは傷つけることにもなるので慎重に行いました。
- ・知識だけでなく、体験することの大切さを実感した。
- ・土に触れることができてとてもよかった。
- ・とれたての春菊が柔らかくてとてもおいしかったことに感動した。
- ・今まで知識だけだったこと(嫌気呼吸や光屈性)が農業に生かされていることを知って感動した。
逆に(実家が農業で)実践していたことに、理論的裏づけがあることを知って驚いた。 - ・それぞれの農業実習の時間が短かった。一泊二日、二泊三日でもいいからじっくり取組みたい。
- ・「食べる」ということは生きる上でまさに基本だが、思っていた以上に自分の食べているものに対して無知であったことを痛感させられました。
- ・毎日無意識のうちに「食べる」ということを繰り返していますが、自分が今食べているものはどのようなもので、どのように作られたのかということを常に頭の片隅におけるようにしていたいです。
- ・日本であまりに簡単に食べ物が手に入る中、様々な意識や知識が失われていったように思います。「食」が脚光を浴びるようになった今、再びたくさんの人が食に目を向け、そして食に関して他人任せでなく当事者であるということを思い起こさせるような、そんなお手伝いが出来るよう4月から仕事を頑張ってゆきたいです。