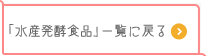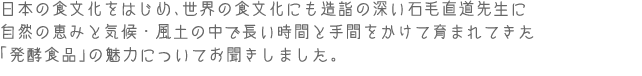
生の魚介類に大量の塩を加えて腐敗を防止しながら長期間保存すると、ぬるぬるした塩辛になります。原料の魚介類にふくまれているたんぱく質分解酵素が作用して、魚肉の一部が溶けて、ペプチドやアミノ酸類に分解します。そのことによって、生の魚には含まれてなかったアミノ酸の「うま味」が生じるのです。塩辛は塩味と「うま味」をもつ保存食品なのです。
現在では、塩辛を酒のさかなの珍味として食べる消費が主ですが、かつては、手軽な飯のおかずとして食べられていました。また、塩辛と一緒に野菜を煮たり、塩辛を漬けたカメから汁をすくって、醤油のように利用することもおこなわれていました。塩辛は調味料でもあったのです。現在でも、東南アジアでは塩辛は重要な調味料として、料理の味つけにもちいられています。朝鮮半島のキムチの漬けこみに塩辛を混ぜて、味をよくすることがなされます。キムチから間接的に塩辛を食べるので、韓国人の塩辛消費量は、成人1人あたり1カ月0.5キロ以上だといわれます。
塩辛を長い間置くと、魚肉の分解が進行し、どろどろの半液体状になります。それを漉して、液体部分だけをあつめたのが魚醤油です。秋田のしょっつる、能登半島のいしる、香川のイカナゴ醤油が有名ですが、かつては日本の各地で魚醤油がつくられていました。タイのナム・プラー、ベトナムのニョク・マム、フィリピンのパティスなど、東南アジア各地で魚醤油の製造がさかんです。
魚醤油を「魚醤」と表現することがあります。しかし、もともとは魚醤という文字は「うおびしお」と読み、塩辛類一般をしめす名称でした。ここでは、塩辛を液体状にした調味料を魚醤油ということにします。
塩辛は考古学的遺物として残らないので、いつから日本人が塩辛を食べるようになったかを実証することは困難です。藤原京(694-710年)跡から出土した木簡に、「フナのししお」と読める、フナを原料とした塩辛が記されているのが最初の文字記録です。その後、海産の魚を原料とする塩辛が主流になりましたが、平安時代の記録にはシカ、ウサギを原料とする獣肉の塩辛も現れます。
東南アジアや中国にも、獣肉の塩辛がありました。インドシナ半島や中国では、歴史的には海産魚ではなく淡水魚を原料とする塩辛が主流でした。それが海にかこまれた朝鮮半島や日本、フィリピンでは、海産魚介類を原料とする塩辛に変化したのです。
塩漬けにした魚を米飯に混ぜて置いておくと、乳酸発酵をして酸っぱくなり、長期間保存できる独得の風味をもつ食品になります。これがなれずしです。なれずしは、ご飯を漬け床にした、魚の漬け物のような食品です。酸っぱい味がするので、「酢し」というようになったのだという「すし」の語源説が有力です。
琵琶湖のフナずし、長良川のアユずし、和歌山県のサンマのくさりずしなどが有名ですが、かつては日本各地で、なれずしをつくっていました。特定の漁期に集中して漁獲される魚を保存食品化して、いつでも食べられるようにしたのが、なれずしです。祭りや行事のご馳走に魚を欠かすことができませんが、時化で魚が手にはいらないときもあります。なれずしにしておいたら、いつでも食べられるので、行事食になれずしが供されることがおおかったのです。
8世紀前半の『養老令』に鮓の文字が現れるのが最初の記録です。長い間、なれずしは鮓、あるいは鮨という文字で表記されてきました。「すし」といえば、なれずしのことだったのです。平安時代の記録には、海産魚介類のほかに、アユ、フナ、アメノウオの淡水産の魚を原料としたなれずしが現れることに注目されます。
室町時代から、日本のすしは独自の発展をとげることになります。なれずしのご飯は酸っぱく、ベトベトしているので、飯粒を取り去って食べるのが普通です。室町時代に、ご飯も食べられる「生なれ」ずしが出現したのです。漬けこんでから、はやい場合は3-4日、おそくとも1-2カ月で消費するのが「生なれ」です。魚はまだ生々しく、ご飯の飯粒も酸味がでるか、でないかの状態で、魚と飯を一緒に食べるようになったのです。なれずしは魚だけを食べる副食物や酒のさかなでしたが、「生なれ」になると、主食と副食物が一体化した「食事」になったのです。
江戸時代中頃になると、魚や飯に酢を加えて、酸っぱくしたすしが現れます。19世紀前半の江戸の街で、握りずしの店が繁盛し、お客の顔を見てから、すしをつくることになりました。保存食品だったすしが、インスタント食品に変化したのです。
発酵させないでつくる握りずしや、海苔巻きずしが「すし」と呼ばれるようになると、伝統的なすしが、「馴れずし」、「熟れずし」といわれるようになったのです。それでも、酢で酸っぱくしたすし飯をもちいることに、かつての乳酸発酵食品の名残をとどめています。
右の世界におけるなれずしの伝統的分布図をご覧ください。中国が点線で示されています。1世紀末頃の中国の記録に、なれずしが初出し、10世紀頃には漢族もなれずしをよく食べていました。中国の食文化の特徴は、現代に近づくほど、生ものを食べなくなり、火熱で処理した料理だけを食べる習慣が確立したことです。そこで、生のまま魚を食べる塩辛やなれずしは、現代では忘れられた食品になり、西南中国の少数民族にわずかに残る食べ物となってしまいました。
現在でも、東南アジアではなれずしがよく食べられ、インドシナ半島の市場では、淡水魚を原料とした既製品のなれずしが売られています。また、東南アジアにおけるなれずしの分布圏は、塩辛をよく食べる地帯に一致します。
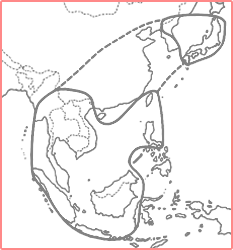
東南アジアにおけるなれずしの分布は、15世紀における水田稲作の分布にほぼ一致します。さまざまな理由から、塩辛となれずしはメコン川の中流地域から中国の雲南省、貴州省にかけての初期の水田稲作地帯に起源する食品であると、わたしは考えます。農薬を使用する以前の水田と、それに続く水路は淡水魚の漁獲にもってこいの環境です。わたしは、稲作と淡水漁業がセットになった生活様式を、「水田漁業」と名づけました。塩辛となれずしは水田漁業に起源する食品であると推定されます。一時期に集中して漁獲される淡水魚を保存する技術として、塩辛、なれずしが開発されたのです。
そして、水田稲作の伝播とともに、塩辛、なれずしがアジア各地に伝わったもののようです。日本で本格的な水田稲作が開始される弥生時代から、淡水魚の塩辛、なれずしが食べられていたのではないかと、わたしは考えています(参照:石毛直道・ケネス ラドル『魚醤とナレズシの研究ーーモンスーン・アジアの食事文化』 岩波書店 1990年)。

石毛直道氏
国立民族学博物館名誉教授、農学博士。世界の食文化研究の第一人者。単著に、『麺の文化史』『石毛直道 食文化を語る』などがある。